ダリヤ・ドゥギナ:私たちは精神革命を必要としている
プライマリータブ
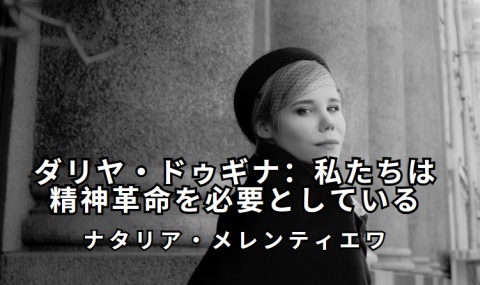
「上昇のための覚醒 」
現代社会での生活は、私たちに膨大な努力を求めます。それは単なる日常の活動や身体の動きだけでなく、心の力、思考の力、そして知性の努力についても言っているのです。「知的労働」とは、聖なる父たちが修道士の実践でこれを呼んだものです。そして、この労働は、私たちが毎分、世界が識別不能な混沌に溶け込まないように、善と悪、価値あるものと価値のないもの、偶然性と運命性を識別するため、プラトン主義者が言ったように、ディアクリシス(識別)を行うだけでなく、世界を意味で満たし、その構造化、設計、目的設定を行い、比率を保つためにも必要です。この作業は、エントロピーがすべてを一様な混沌に変えるのを防ぐためにも必要です。
私たちは、完全に破壊され、歪められた世界で生きています。私たちは、全ての比率が歪められた、断絶した文明に生きています。その背骨が折れ、垂直性、上位の階層についての観念が破壊されています。そして、知的な緊張は必要であり、それがプラトンやプラトニック思想者たちが描いた理想的なモデル、知的に整然とした階層的な世界の比率を修復するためです。
ダリヤ・ドゥギナが自身のテレグラムでの電子日記に書いていました。「私たちはこの世界に投げ出されています。[1]私たちには義務と使命があります。私たちには、内面の革命、精神の革命が必要です。」[2] そしてまた別の場所で「私たちは、垂直の覚醒の中心軸にいます。」[3]
しかし、さらに激しい内面の革命が、さらに大きな知性の努力が求められています。それは、人間が思考する能力を開く、または覚醒させるためです。思考を模倣するのではなく、真に思考すること、最も深いことを思考すること、本質的なことを思考すること、完全な思考の領域へと侵入することです。なぜなら、計算的な理性や、表面を滑るような現代的な流暢な言葉、それが賢者たちが「思考」と呼んだものを模倣することは、全く満足の行くものではなく、実際には人類を深淵の縁にまで追い詰めてしまうからです。
ダーシャは哲学者の家庭で育ち、その中で人格を形成しました。幼少期から彼女には思考する方法を教えてきました。彼女が大人になったとき、哲学、つまり思考の本質を運命として選びました。
20世紀の偉大なドイツの哲学者、M.ハイデガーが「思考とは何か」という問いを新たに立て、そのテーマに対して鋭く、複雑な議論を展開しました。彼はこれについて、最も神秘的な作品の一つである「Was heisst Denken?」を書きました。我が家では、この作品を知性を持つ者にとっての一種のイニシエーションの道と見なしていました。アレクサンドル・ドゥーギンは、このドイツの思考家にいくつかの本を献じました。ダリヤは特に、ハイデガーの革新的な主張、すなわち人間の基本的性質である「思考」をディコンストラクションに置くことに感銘を受けました。
しかしここで一つ、「しかし」という点があります:ハイデガーは名目上、正統的なプラトン主義、特に物事の理想的な模範としてのアイデアの超越性について反対していました。彼は、先生プラトンに対して反旗を翻したアリストテレスにはるかに近かったのです。アリストテレスは、「上-下」の軸(プラトンの「ティマイオス」、「国家」などの対話に見られる)ではなく、「中心-周辺」[4]のラインに沿った水平的なオントロジーを構築したのです。この永遠の物語、垂直と水平、神と世界、アポファティックとカタファティック、神々の(一つ、絶対的な)天上的な質と世界内的な質との間の対立は、世界の歴史の中で多くの哲学者たちの争いと不一致の原因となりました。ダリヤはこの対立性を自身に当てはめ、垂直と水平の形而上学の複雑な絡み合いを理解しようとしました。プラトンは彼女にとって精神的に親しい存在でしたが、現象学者たちの水平的なオントロジー、そして特にマルティン・ハイデガーの洗練された思考も彼女を引きつけていました。
ダリアは、自身の音楽プロジェクトにハイデガーの哲学の中心的な要素である「Dasein」「存在すること」を引用し、「Dasein may refuse」と名付けました。ハイデガーは、「Dasein」を、思考する存在としての人間が世界に直接存在するという意味で使用していました。しかし、これについては後ほど詳しく触れましょう。
ダリアは、モスクワ大学の哲学部で外国哲学史の専門科を修了しました。彼女は歴史哲学のプロセス、つまり、そのパラダイムの基盤、目的論、策略、微細な差異を理解し、その意味を把握しようと努めていたのです。
「プラトノワ」というペンネームの意義
彼女は「プラトノワ」をペンネームとして選び、青春時代をプラトン主義の研究に捧げました。キリスト教徒や他宗教の各種プラトン主義者、新プラトン主義者の著作や理論を深く学びました。かつてアメリカの哲学者A.ホワイトヘッドは、全世界の哲学はプラトンのフィールドノート以上のものではないと指摘しました。プラトン主義に没頭することで、我々は歴史、文化、思考、理性の生成、意味の創造、構造形成の問題の核心、すなわち嵐の目に到達するのです。ダーシャはこのことを知り、表面的であれ危険なこの道を選びました。
人々はしばしば知性を恐れ、火のように避けます。かつてアテネの市民はソクラテスを死刑に[5]、アレクサンドリアの住民はヒパティアを殺しました。現代では、世界の支配層が自由な思考を激しく忌み嫌っているのと同様です。事実、現代世界では思考の軌道は徐々に狭まり、「大きな物語」は蔑みの対象となり、哲学の研究は意図的に微視的な詳細への技術的な分析に変えられています。一般化は許されていません。そして当然、この認識論的な分断の策略の最初の標的は、プラトンとプラトン主義者の広範な概要でした。彼らは文字通り、「キャンセルカルチャー」の戦略に翻弄されました。
しかし、ポストモダニズムによる最新の思考への攻撃や、極めて反転した対象指向オントロジー(OOO)の逸脱さえも、哲学者への迫害の終わりや最後の言葉とはならないでしょう。
今日の世界では、支配的なエリートによって知識人としての場所を割り振られたことに満足せず、真に自由な思考の尊厳を堅持する哲学者たちが、意図的に、そして狙われて命を奪われています。ダーシャは、このような退廃への対抗策として、まず思想、理念、新たな観念、計画、プロジェクトが必要であると理解していました。そして彼女は、この戦いの出発点としてプラトン主義を選択しました。この道程が容易ではないことを彼女は予想していましたが、その難しさや最終的な結末を彼女自身が予見することはできませんでした。彼女は哲学者が命を奪われることを知り、そのことを自身の論文や日記に書き綴っていました。しかし、彼女自身が哲学者であり、それが彼女自身の運命であることを、彼女自身が完全に認識していたかどうかは不明です。そしてそれが、自由に選ばれ、短いながらも明るく純粋に生き抜かれた彼女自身の運命であったのです。
「プラトンの余白に描かれた覚書」
ダリア・ドゥギナの哲学的テキストや政治についての記事、さらには彼女の日記を読む際、彼女の思考の明示的・暗示的な座標軸がプラトン主義であったことを理解することが重要です。ダーシャは、プラトンの対話録に飛び込むことを喜び、それによって新たな驚きの洞察、深遠な発見、微細な論理と論争のニュアンスを何度も見つけました。
プラトン主義は、2層構造の調和した、連続した世界を築きました。上層にはイデアや模範、物事や世界の出来事の形態が存在し、下層には物質と物そのものが存在しています。下層の物質と物そのものは、イデアやロゴスを観照し、それらを天上の模範として模倣しています。こうして、天と地、そして最上位のイデアである「善」、あるいは「語り得ぬもの」、「言葉に出来ぬもの」、「唯一なるもの」といった概念によって繋がれたイデアの階層が形成されました。
プラトン主義は世界の知的な構造を描き出し、その中で人間は、模範やパラダイム(イデア)の世界と現象(物事や出来事)の世界という二つの世界を繋ぐ媒介者として立っています。そして、全体のシステムは上部が開いており、「唯一なるもの」が表現不能な、名前をつけることのできない、存在そのものに先立つ何かとして想定されていました。そして、宗教においては、この「唯一なるもの」が神として理解されていました。
超越的な「善」、あるいは「唯一なるもの」の微妙な保護の下で、世界は構築され、天の原型が反復され、物事は生み出されています。そして創造された物事や存在、特に最も高貴で完全なもの、すなわち人間と天使は、イデアを瞑想し、自身の起源へ、天の故郷へと戻る道を探し求めています。それは出発と帰還という永遠のリズム、それが聖なる世界の模式です。この模式は何千年もの間存在し続けてきました。その構造、階層、昇降の階段は多くの世界宗教に見られます。
人間はその中で、霊、善、真理、美、正義へと昇っていき、時折戻り、そして再びヤコブの梯子、すなわち霊的完成の階段を上っていきます。人間の上昇、その完全化と変貌(キリスト教における「神化」)こそが、人間の最高の目的とされています。
ダリア・ドゥギナの哲学、世界観、個人的な文化コードにとって、この霊的な世界の模式こそが存在論的な地図と方位を示していました。彼女が選んだ名前にさえ、プラトンは常に寄り添っていました。
ジル・ドゥルーズが指摘するように、「全面的な成長」の世界は、言語の流動性を示唆しています。この世界では、名詞はより活動的で動きのある動詞に取って代わられ、意味や概念が成長の雪崩のような力によって溶けて消えていきます。また、現代の若者が一貫性のある思考や論理的な意見表明を行う能力が欠けているのは全く当然であり、スラング、方言、専門用語、身振り言葉への依存は、最終的に無言、無表情となり、反応も責任もない状態へと導くと言えます。
インターネット空間は、厳密な解散のアルゴリズムに従って構築されています。これには「ニックネーム」の変更、ジェンダーの変動、匿名性、罰せられることなく、下品な言葉、攻撃的な行動、他者への侮辱や迫害が含まれます。これは「電子ジャングルの根茎」という現象を生み出し、新世代のメンバーほど、彼らの意識の構造に深くウェブが入り込んでいきます。結果として、オフラインの世界はオンラインの単調な影となり、現実はバーチャルな世界の模倣と化してしまいます。
「ポストモダンの断片」
「政治」における対話にも触れているように、プラトン自身が鮮やかに描き出すこの概念により、被造物がその創造主から離れていくとどのようなことが起こるかが語られています。実際に、ほとんど全ての宗教は、終末の「オメガ・ポイント」が近づくにつれて、世界と人類が退化し、劣化し、精神的な特性を失い、元の模様から遠ざかると主張しています。近代が到来し、その後にポストモダンが続きました。そして、ダリアのような伝統主義の哲学者の視点から見れば、西欧の新時代は、急速な衰退、分裂、意味と目的の喪失というプロセスとして映っていたのです。一方で、ポストモダンは、文明の退化という流れの中で必然的に訪れる結末と見えたのです。
20世紀のフランスのポストモダニストであるジル・ドゥルーズは、プラトンをあざ笑うように、その著作の余白からプラトンの視点を逸脱し、歪めるという手法を採用しています。彼はプラトン主義がイデアと物質の二元論を語るのではなく、物質の中でイデアに対応するコピーと、イデアから完全に離れ、それらから逃れる存在の二重性を語るのだと主張しています。つまり、形や定義から逃れて滑るように存在するものが、この世界には確かに存在するというのです。ドゥルーズはこれを「純粋な存在」、「無限」、「コピーの影」と表現し、ボードリヤールはそれを「オリジナルのないコピー」、つまり「シミュラクル」だと呼びました。
プラトンへの深い忠誠を持つダリアは、これらのポストモダンの歪んだ、反転した存在論に興呪を持ちました。彼女はその複雑さを理解しようと試み、その偽物の本質を突き止め、彼らの皮肉を解読しようとしました。これらの理論的な建築物は虚偽であるとともに、何か催眠的な魅力を持つところがあり、それらは皮肉な流出、ずれ、そして越境に基づいています。ダリアは、これらの配置がどのようになされているかを理解しようとしました。
現代の世界で人々とコミュニケーションを取る際、ある特異な感覚がしばしば訪れます。それは、あらゆる思考、発言、コメントが、そこに何らかの明確さや現象の最小限の構造化の試みが含まれると、それが人々に伝達された瞬間、どこか深淵、暗闇へと吸い込まれていく感じです。これは、明確さへの無意識的な抵抗のようなものです。人々はプラトン的な秩序、階層、精神的な規律、構造、本質の理解から隔離されています。言い換えれば、一般的に人々は思考から遠ざけられています。現代のリベラルな世界は、自由とは無秩序であり、混沌であり、むやみに表面を滑ることだと暗示しています。そして、その暗示は、無意識的にも意識的にも受け入れられています。
ダーシャはしばしば、何人かと(多くは偶然の人々と)会うと、彼らが常に変化し、純粋になろうとしている人々、全くアイデアに従わない人々、つまりアイデアのない人々であるかのような印象を抱くことを悲しく思っています。彼らは、「無限」で非構造化された心を持ち、現在の一瞬、一瞬の関心の瞬間に「漂って」いるようです。そのような人々は、アイデアそのものをあまりに「強力な」現実と見なし、価値の階層から身を引く、またはそれから逃れる傾向があります。そして最も重要なことは、彼らがその結果として本当の自由を保持していないということです。より正確には、この人間の流動性こそが暗黒の自由と言えるのです。
自身の世代、身の回りの環境、知人たちの中に見られるポストモダンの典型的な産物を観察するダリヤは、これら明らかに断片化しフラクタル化された存在を、彼女が理解する完全なプラトン的な個性と何とか結びつけようと努力しました。この取り組みは困難であるとはいえ、彼女は決して諦めることなく、日常的で時には陳腐な人間関係や状況に哲学を導入し続けたのです。
「暗黒の自由」
ドゥルーズによれば、イデアやロゴスから掴みどころのない人々や物事は、一見すると何の基準も持たないかのように見えます。しかし、その基準は彼ら自身の下、つまり存在の底辺に存在しています。彼らはまるで催眠術にかかったかのように、物事がロゴスから、すなわちイデアの世界から得るべき秩序の裏側にある狂乱の要素に魅了されています。彼らはまるで覚醒していない物質の魔法にかかっているかのようです。
ダリヤは生涯を通じてプラトンを愛し、その思想を研究してきましたが、ジル・ドゥルーズの哲学にも深く敬意を抱いていました。哲学部での学生時代に彼のテキストを熱心に読み、その後も度々それに立ち戻っていました。
ジル・ドゥルーズは意図的にプラトンの二元世界観を変えています。一つはイデアや「エイドス」、精神的存在の世界であり、もう一つは現象、複製、成長と上位の「理知」の世界を反映する世界です。新しい時代の名目主義者たちに続いて、ドゥルーズは世界理性(ヌース)によって支配されたプラトンの精神的な宇宙を無効にし、その慎重さ、自由の欠如、暴力、全体主義を拒否します。そして実質的には「時代遅れ」を否定しています。ポストモダンでは、世界は全体として一貫性のない豪華なアンサンブルに変わり、流動的でぼんやりとした空間になります。そこでは意味が滑り落ち、停止することなく、互いに関連性のない「解き放たれた」集合になります。[6] これは「純粋な量」の新しい素晴らしい世界であり[7]、動きと「反乱的な成長」の流れの広大な空間であり、今や廃止された精神的な原型への回帰も、物事と意味の意図的な溶解の流れの中で永遠の真理の反射を定着することも排除しています。
ポストモダニズムの擁護者たちは、不確定性に満ちた流動的な世界観が、「開放された社会」の人々や普遍的解放の理念にとって魅力的だと主張します。ポストモダン哲学は、過去と未来の意義の統一性、あらゆる事象の「前」と「後」の世界の混在、そして過剰と欠如の交差という、「成り立ち」のパラドックスに私たちを立ち向かわせます。それは、罪と罰、多いと少ない、善と悪の間で何でも互いに入れ替え可能な空間です。
この空間は、名前を失い、知識の一貫性を拒む場所であるかもしれません。また、「個人の自我は平和と神を必要とする。しかし、名詞と形容詞が融解し始め、休止や停止の名前が純粋に進化する動詞に取って代わられ、出来事の言葉に滑り落ちると、自我、神、世界のいかなるアイデンティティも消滅する」と言います。[8]
つまり、ポストモダニストたちは私たちに何も確定的な保証を与えず、神、世界、自我との別れとともに流動性の中で生きることを勧めるのです。我々に提供されるのは「環境」、「メディウム」(もはや「世界」ではない)で、そこでは垂直性が存在せず、樹木の象徴としての垂直軸や階層が、目指す先が不明な根茎の領域、つまりはジャガイモのようにどこへでも伸びていく塊茎に置き換えられています。
これらの深遠な自由は、結果として魂を失うという代償を伴います。それではダリヤさん、ゼィグムント・バウマンの「流動する社会」やマヌエル・カステルスの仮想世界、つまりネットワーク社会へと足を踏み入れてみましょう。
これは、おそらく「悪」へと道を開く招待状とも言えるかもしれません。
「菌類の特性を持つ人間」
「リゾーム」は一般的には、木の垂直構造に対するつながりの水平構造として定義されます。1970年代後半に、分散型ネットワークのモデルとしてのリゾームが登場しました。これは生物学、特に菌類の根系からインスピレーションを得たもので、その特徴は非中央集権的な状態と、結びつきが増え続け、予測できない出会いや偶然の出来事がネットワークの性質を変えるという、意図しない成長にあります。
予測できない出会いや新しい情報は、あらかじめ設定されているわけではなく、ネットワーク内には経験や類似性の文脈が組み込まれています。インターネットが組織化された社会では、どのノードも新たな変化の起点となり得ます。
これら全ては、ロシアの哲学者たち、特にロシア科学アカデミー哲学研究所のメンバーによって、批判的な視点を欠いたまま受け入れられてきました。彼らは、ポストモダンとその戦略に敬意を表し、「暗黒の自由」を賞賛しているかのよう
印象を与えます。これは、彼らの大半の著作から感じられるものです。
一方で、ダリヤはモスクワ大学の哲学部を最高の成績で卒業し、ポストモダニズムを含む各分野での能力は明らかでした。しかし、リベラルなポストモダニズムの退廃に巻き込まれたロシアの哲学者たちのコミュニティと共通の言語を見つけることはできませんでした。その理由としては、彼らの大部分が(もちろん全員ではありませんが)、本格的で、それゆえに垂直的で、永遠を見つめる思考との最後のつながりを断ち切り、さえもプラトンの領域を離れてしまったからです。
確かに、一見無邪気な弁明や、非中心性、混沌、不確実性の原理を推進し、創造的な新しさの瞬間やネットワーク型根茎の創発的性格を強調していますが、これらは水平リゾームが必然的に限定され、排他的であることを控えめに伝えているのです。すべての伝統的、宗教的、古風な文化型、非西洋文明によって生み出された豊富な知的財宝と文化世界の豊かさが、これらの土台となっています。また、これは前近代や近代の西洋自体も同様です。
ポストモダンの自由と創造性の名のもとでは、善であること、神、信仰、伝統、存在論、形而上学、永遠、意味、本質、根ざすこと、道徳、同一性といったものは許されません。なぜなら、「暗黒の自由」は、壮大な禁止事項という巨大な全体主義の基盤の上に成り立っているからです。つまり、あなたには、「暗黒の自由」以外の何ものにも権利を持つことができません。
この結果、菌類、根茎、狡猾なカビのコロニーが人類の運命となってしまいます。下に進むこと、上に進むこと、右に進むこと、左に進むこと、すべてが排除の対象となります。これは取り消し、デプラットフォーミング、追放、恥辱の行為であり、それでも解決しない場合には、車の爆破といった手段まで取るのです。
ポストモダンのリゾーム戦略は、遠慮がちに多くの制約を隠蔽し、二重基準に基づいています。非人間化された大衆には、「リゾーム」(混沌)、脱イデオロギー化、理念や原則、イデオロギー、階層、プロジェクトがない「流動的な社会」が提示され、これらは全体主義的な垂直性の遺跡と見なされます。対照的に、西洋の衰退した国々からの未来の設計者や管理者となる、いわゆる「世界のエリート」に対しては、厳格で一貫したポストヒューマンとポストヒストリーのイデオロギー、あるいは神話が形成されています。この二重基準の問題は、今日、真の姿を明らかにし始めています。それは西洋のエリート集団が、人工知能と「人間リゾーム」の概念と共に、すぐに一般的な遺伝子改変のプラットフォームで消え去ることになる一方、未だに消えていない、近代化されデジタル化されたプラトン的な垂直構造を保持する他の人類との間の大いなる闘争です。これらの構造は、時々「伝統的な価値観」と呼ばれるのです。
「形を失った言葉」
ジル・ドゥルーズが指摘するように、「全面的な成長」の世界は、言語の流動性を示唆しています。この世界では、名詞はより活動的で動きのある動詞に取って代わられ、意味や概念が成長の雪崩のような力によって溶けて消えていきます。また、現代の若者が一貫性のある思考や論理的な意見表明を行う能力が欠けているのは全く当然であり、スラング、方言、専門用語、身振り言葉への依存は、最終的に無言、無表情となり、反応も責任もない状態へと導くと言えます。
インターネット空間は、厳密な解散のアルゴリズムに従って構築されています。これには「ニックネーム」の変更、ジェンダーの変動、匿名性、罰せられることなく、下品な言葉、攻撃的な行動、他者への侮辱や迫害が含まれます。これは「電子ジャングルの根茎」という現象を生み出し、新世代のメンバーほど、彼らの意識の構造に深くウェブが入り込んでいきます。結果として、オフラインの世界はオンラインの単調な影となり、現実はバーチャルな世界の模倣と化してしまいます。
ダリヤは、若者たちがインターネットやゲーム、ありふれたメッセージ交換やInstagramのブラウジングに時間を浪費することに大いに失望していました。「Instagramを自制できないのなら、それは大いなる力によって閉じられるべきだ。本に向かいましょう、本に!本に!本に!」[9]と、彼女は日記に記しています。しかし、彼女の拒否感は外部からのものではなく、内部からのものでした。客観的な理由から、彼女自身がその文化的環境の一部であり、生活の中心にインターネットやソーシャルメディア、デジタルデバイスを置いている同世代の人々に囲まれていました。ダリヤの言葉、「自制できない」に注目してみてください。これは、早い段階からスクリーンや仮想世界と結びつき、その影響を最も強く受けている新世代に対する、デジタル化の暗黒の力への重要な認識を示しています。
ダリヤは、このような「暗黒の自由」の世界を解読しようと努めていました。しかし、必ずしも成功するわけではなく、時には人々との関係が誤解や困惑、意図やコミュニケーション戦略の誤解を招くこともありました。ダリヤは現代的であり、アートやファッション、革新的な創造的な実践に向けて前衛的な探求に開かれていました。しかし、同時に、彼女は至る所で社会心理的な織物の崩壊を進行させるポストモダンの「折り目」、根源的な結びつきの振動、個人を超えた魅力の引き寄せを認識していました。これらは人々が自己の一貫性やアイデンティティを維持するのを阻むばかりか、積極的にそれを破壊する力になったのです。
「対象中心の存在論としての物語」
ポストモダンが哲学的な垂直志向の宇宙の解体の究極と思われがちですが、それは実はそうではありません。ドゥルーズの後に続いて、オブジェクト指向存在論(OOO)または「思弁的実在論」と一般的に呼ばれる、さらに過酷な哲学的戦略が登場しました。
この文脈でも、ダリヤはF. ニーチェの原則に従って行動しました。彼の言葉によれば、「真理の水が浅い時、それこそが真に知る者が水に飛び込むことを嫌う瞬間である。」[10]だからこそ、彼女は現代思想のこの流れに関心を持ち、特に、レザ・ネガレスタニやニック・ランドといった思想家たちの考えに興味を示しました。彼らは、超物質主義をさまざまな、時折エキゾチックな神話からの象徴やキャラクターに対する言及と組み合わせて展開していました。
ダリヤはこの思想の流れに、逆さまになった伝統主義を見つけ出しました。プラトニックな伝統主義者たちは、歴史の終わりに世界の卵が下から割れ、肉体の下限から闇の「ゴーグとマゴーグの軍勢」[11]が溢れ出すことを予告していました。ダリヤは彼らを、投機的な現実主義者として容易に見抜いたのです。
「オブジェクト指向の存在論者」は、ポストモダニズム、それ自体に対して攻撃を開始しました。ポストモダニズムでは、人間の主体性がいくらかは溶け込んでいても、それでも一定の位置を占めていました。彼らは、古典的唯物論をその論理的な限界まで推し進めることを計画しました。それにより、今度は「存在の過程」そのもの、すなわち、無秩序で目的を見いだせないものが批判の対象となりました。その存在の過程には、生命が過剰に存在し、それ故に散在し、溶けてしまうものであっても、主体性があるとされました。全ての主体性を完全に撤廃すること、それが思弁的実在論の目指す目標でした。その目標は、物事自体の視点、そしてそれらの内部から世界を描き出すことにありました。
この倒錯した試みでは、反思考の構造を築き上げることを目指して、人間だけでなく、存在や生命そのものも問い直されました。それらは、絶えずダイナミックな差異の対立を引き起こすものでした。思弁的実在論者たちは、物事の内部深くにあるものは、このような分裂を「知らない」と主張しました。それらは何とも相関していないのです。それから、すべての相関主義への批判が派生しました。
例えば、クエンティン・メイヤス[12]は、我々が人間を思考が行われる特権的な認識論的存在であり、そのために認識が行われるという長年の誤解を指摘しています。我々は、人間を超越的な知識の保有者、先天的に与えられたカテゴリーや原則、アイデアの所有者と考えてきました。しかし、実際には神も、神の代理として地上にいる人間も、超越的でも超越論的でもないことがわかりました。そこに存在するのは、「束縛のない虚無」(nihil unbound)[13]とその円環で、それらは今なお「物体の世界」と呼ばれています。しかし、その呼び名さえもすぐに消えるでしょう。
ニック・ランド[14]は、我々の文明が石油やガスを求めて掘削に執着する結果、地球の核が崩壊し、地殻を突き破り生命に終止符を打つと主張しています。彼はこれを「核の苦悩」が有機体の細胞へと発展し、人間へと進化し、さらには自己を超越する人工知能へと進化する文明の象徴と捉えています(これがダーウィニズムと生物学的理論が導き出す結果だと彼は言います)。そして、地獄のような大変動の後には、かつて地球だったものの燃え尽きた残骸だけが太陽へと向かって突進し、無意味な物質的存在のもう一つの燃え尽きた断片を襲いつつ進むのだと彼は語ります。
ダリヤは、この反神話の魅力にある程度取り憑かれ、一部のソーシャルメディアでは皮肉混じりに「ニック・ランド」の名を使っていました。彼女は自身の秘密の日記をTelegramチャンネルに掲載し、「オレオナフト」と名付けていました。これは、もう一人の思弁的リアリスト、レザ・ネガレスタニが提唱する近代の神秘的な技術文明における燃料油の役割に魅了された結果でした。ネガレスタニによれば、井戸の掘削は地球の核からの「メッセンジャー」とも言えるネズミの行動を継承しています。ネズミは地球の地殻の完全性を穴だらけにし、地球の核の開放と太陽への送り出しを援助するとネガレスタニは主張しています。石油に取り憑かれた「採掘」[15]の人間は、歴史的プロセスの潤滑油となり、地球の核の解放と太陽への送り出しを助ける存在となるのです。
しかし、ダリヤの対象存在論の不適格者や狂人たちへの哲学的、人間的な同情は、彼らが現代世界の地獄のような本質とグロテスクな運命についての重苦しい思索の負担を引き受けていたとはいえ、彼女の伝統主義者としての責任が常に上回っていました。この責任とは、現代世界で見捨てられ、腐敗してしまった人間性に対するものです。彼女自身が現代世界に反逆する責任を自覚し、その堕落のどの局面からでも、人間の存在が低下するどの境界からでも反抗を主張していました。彼女は特に自分の世代に対する懸念を強く感じていました。
彼女は自身の日記に「友達よ、私たちは偶然にこの世界に放り出されたわけではありません。もし私たちが感じなくなり、自己を見失い、世界から切り離され、ばらばらになっていくなら、我々は遠くへ行くことはできません… 我々に必要なのは、自己の統一を保つ形式としての内面的な攻撃性、そしてそれを養う形式です」と書いています[16]。さらに、「人間の魂の力は、限界のないところに存在します。まるでアッティラが西へと進んで夕日を目の当たりにしたように。私は自身の弱さに対して無慈悲であり、内部の空間を征服し、全てを破壊するつもりです…」と続けています[17]。
伝統主義者であるダリヤにとって、現代世界とその哲学が人間の自我を完全に解消しようとする強い誘導力を持つことは、明らかでした。ジル・ドゥルーズは、かつて「具体的なもの」として考えられていた世界の事象に、すでに存在しないが一瞬だけ現れを保持し、存在の最小限を持つ、表面的な効果や出来事しか見いださなかったのです。一方、対象指向の存在論者たちは、さらに一歩踏み込み、存在を失い、崩壊しつつある人間が自己の特異性についての抑えきれないナポレオン的自負心を持つと非難し、彼に対する巨大な対象の反乱の火災での滅亡を予言しました。
ダリヤは微妙に感じ取っていました、人々があっという間に、虚無の表面で紙切れがさらさらと音を立てるような存在や、物体の縁で跳ね回る霧のような存在に変わりつつあることを。原因も目標も計画もなく、全体性や垂直性の概念がなく、神についての知識もない全体性の欠如した世界では、人間は確かに絶望的であると。
「自己認識の統合」
ダリヤは、現状下では、私たちは人工的かつ強制的に主観性を結集することが求められていると考えていました。彼女は、人間が破滅の面前で、多種多様で場合によってはグロテスクな手段を用いて、伝統によって遺産とされる悔い改めへと進む道を探ることが許されると主張しました。その手段には、儀式(教会、文化、日常生活)、集中的な読書と思索、先延ばしや怠惰の克服、スーフィーのように「自分の隠されたカリフへの隠遁」、身体の練習、スポーツ、食事や睡眠の管理、そして精神のコントロールなどが含まれていました。
ダリヤは、本から詩、哲学、思考、感情の反応、苦悩、服装の着こなし、ヒールやドレス、食事、人間関係、身体、化粧品まで、全てが儀式になるべきだと信じていました。彼女は、自分の人生の文化的な空間を非常に鮮やかで、統一され、完全なものに変えることを目指していました。「少なくとも足の不自由な靴、ハイヒールを選ぶ、あるいは少し締め付けて体の全体を引き締め、背筋を伸ばさせるドレスを選ぶ人は、まさに美しい」と彼女は述べています。「その意味で、バロック時代のドレスの枠組みや、それだけでなく、他の多くのものが顕現し、表現する絶対的な美しさ...」[18]と彼女は記述しています。
さらに、彼女は書いています。「文化的な枠組みで着用されるすべてのものは、何かしらの超越を持つべきだ... 儀式や信仰行為の最中、司祭がどれほど丁寧に服を着て、微細な詳細にどれほどの重要性を置くかを見てください。そして、私たちが単純な日常生活に放り込まれているときでも、同様の行為を行うべきです:常に自然と人間との間に人工的な障壁を作り上げることについて考えるべきです。これを理解し、認識しなければ、私たちはおそらく何か奇妙な物質に分解してしまうでしょう。それは人間以前の存在を思わせるものです。」[19]
ダリヤは、この腐敗や解体との闘いにおいて、中立的なエステティズムや距離感、ダンディズムではなく、自己を超越する強い意志と深い思索を最も重要な要素としています。そしてさらに、「熱い心」「内なる炎」「反逆の喜び」「作品や行為に没頭し、自分自身を追い詰めること」「自己から火花を切り出すこと」「内在する火花の育成」・・・すべてが、「内なる太陽を保つ」ことへと繋がっているのです。しかし、最も重要な課題は、考えること、思考の技術を学ぶこと、そして全てを再評価することです。
私が言うなら、ダリヤの哲学は、一方でプラトン、他方でポストモダニズムと思弁的リアリズムに跨る、貴重な糸のようなもので、これは信じられないほど豊かな中間地帯を経由して、つまり、現象学とハイデガー思想を巡っているのです。
「政治的伝統主義」
ダリヤは哲学に加えて、政治過程にも深い興味を抱いていました。特に彼女が支持していたのは、政治的伝統主義という考え方です。これは、神聖な伝統の規範、伝統的な価値観、そして原則の再確認と肯定を目指すイデオロギーを指します。ダリヤにとっての理想は「垂直政治」、つまり一元的で中央集権的な権力体制だったのです。
ダリヤが講義やライブストリーミング、テレビの分析番組で提唱していた政治アジェンダには、いくつかの核心的な主張がありました。彼女は、ポストモダンの擬似解放的な論議の背後には、単に人間性の破壊を奨励するだけでなく、その破壊を積極的に構築し、強要する実在の権力構造が存在するという事実を痛感していました。これらの権力は、人間の物質的な本性からの低俗な解放シナリオを提案し、人間以下の行動の採用を推進する一方で、人間の存在論的制約を設け、最終的には人間を人工知能に取って代わらせる土壌を隠然と準備しています。そして、このシナリオを避けられない、代替のないトレンドとして各国に押し付けているのです。
この権力構造は血塗られた戦争を引き起こし、世界に対して、人類が深淵に落ち込むのを今なお阻止している全てからの自由化、つまり絶対的な解放を強制しています。それは自己を検証し、世界を理解し、その中で生きる新たなルールを確立することを自覚して行っています。
ダリヤは自身の演説で常に、人間の自然を超えた「人工的」な定位に注目してきました。これは、私たちが生きる社会文化的な構造、そして特定の価値観や認識論的パラダイムの枠内で人間が生きるという考え方です。これらの視点や基盤は、可能性として変えることができるものなのです。
つまり、人間が直面しているのは物事の秩序そのものではなく、物事、意味、理論、人間の像そのもの、その活動、認識、目標設定の認識と構築への要求の秩序です。これまでの人類の歴史は多様性に満ち、さまざまなパラダイムの中で存在し、多種多様な世界観、世界観、文明を創造してきました。しかし、現代社会では、社会的現実を構築する特権が、未来を設計するグローバルな独占権を主張する「進歩的」な権力エリートへと強制的に移譲されています。
この権力集団は、躊躇うことなく第三次世界大戦を引き起こしました。その名前は、オリガルヒと金融エリートという形をとるアングロサクソン文明です。彼らこそが一極主義、グローバリズム、そして覇権主義、すなわち地球上の全面的な支配を主張しています。
ダリヤは、ロシアが世界の意思決定の中心から受け取っている世界と人間の像が、異なる文明、異なる文化的アイデンティティの産物であり、私たちとは違う、ロシアにとって敵対的な歴史的実践の結果であることを示すことを試みました。私たちが気づくべきは、このパラダイムが私たちや他の民族に強制され、そして権力を用いた方法、攻撩的な方法、血の流れる戦争を通じて、またソフトパワー、文化的な破壊行為を通じて、全体主義的に押し付けられようとしているということです。
ダリヤには疑いの余地がありませんでした。敵対的な文明の「方法論家」や管理者の集団は、理論や予測、策略や悪だくみ、公式なロシアの哲学者や政治学者への「原則と規則」の贈与や賄賂、大衆文化の解放戦略の宣伝を通じて、私たちをこのグローバリストのエリートが望む感覚、思考の形式、行動に引きつけています。
ダリヤは公の場でグローバリゼーションと一極主義の世界の不公正さを果敢に問題提起しました。そもそも、人々の合意や理解なしに推進される想像上の基準やルールは、どこから生まれたのでしょうか?それらは、異なる文化的伝統に生きる異なる国々で変化しないのでしょうか?そして、自らをリベラルと宣言する西側は、なぜ覇権主義の考え方に訴え、国々を統一しようとするのでしょうか?一つの文明の世界覇権の戦略は何なのでしょうか?また、「地球の文化の豊かな多様性」を単調なグローバルゲットーに変えるユートピアの実現はどのような形をとるのでしょうか?
ダリヤは電子日記で、人間性の「豊かな多様性」の美しさや、単調な世界に対する多極世界の必然性について語っています。「リベラル覇権の下での一極主義から、全く新しい世界に移行しています。この新しい世界では、プレーヤーは一人ではなく、独自の伝統、歴史、文化を持つ多くの力強いプレーヤーが存在しています。ここには「普遍的な人間」は存在せず、多くの「個々の人間」が存在しています。」[20]彼女は、自分自身と他人の中に、異なる民族の伝統、文明の歴史、異なる文明の調和のとれた共存という伝統主義のメタ理論への関心を喚起しようと努めてきました。彼女が愛した伝統主義者には、ルネ・ゲノン、ジュリアス・エヴォラ、ミルチャ・エリアーデ、エミール・チョラン、カール・シュミット、アントニオ・グラムシ、パーヴェル・フロレンスキー、ニコライ・トルベツコイ、ピョートル・サビツキーなどがいます。
ダリヤは、アングロサクソン系の西洋諸国において、目的意識を持ち巧みに機能する偽りのプロパガンダの言論に常に困惑していました。では、ロシアではどうでしょうか?私たちが伝統主義、キリスト教、正教、ユーラシア主義、多極主義を推進するように、まるで神から命じられたかのように思えます。これらは、私たちの文明と自然に調和する価値観や体制です。ダリヤの政治的信念は、まさにここにありました。彼女は、私たちが不断の行動を取ることができず、全てのレベルで私たちに攻撃を仕掛けるグローバリストを甘んじて受け入れていると考えていました。
リベラルな思想の強靭な意志に私たちは直面しています。それは自らがイデオロギーであることを隠し、政治、経済、文化、情報空間など、全てが全体主義的に連携していることを偽っています。ロシアはこの状況に対し、全体主義的な反抗をもって対峙するべきです。これは、世界的な古典やロシアの古典の遺産に立ち返るとともに、絶対化と支配欲望が暴走したアングロサクソン文明の教義を注意深く解析し、それを砕くことにより、現代世界に立ち向かうことを意味するのです。
「深遠なる洞察:新たな政治学の展望」
ダリヤは、「スターチャンネル」での短いスピーチや、「第一チャンネル」のリプライ、ラジオ番組やストリーム、数え切れないほどのインタビューで、何か重要で深いテーマについて語ることができた時、自身に「合格点」を与えて大いに喜んでいました。それは哲学や宗教の教義、深遠な政治学、あるいは詩についての話であったかもしれません。例えばノヴァーリス、ジャン・ジュネ、ヘルダーリンのことです。彼女は、あらゆる文化現象を情報の議題の文脈に位置づけることを、自己の勝利と捉えていました。
彼女にとって、哲学は政治の本質で、詩は哲学的概念の深淵へ理解の光を投げ込みました。詩は哲学のもう一つの、秘密の次元であり、哲学は政治の中心核であると彼女は考えていました。これこそが、私たちが彼女を、そして彼女だけでなく、私たち、彼女の両親であるアレクサンダーと私が、若者の世代を思考し、書き、講義し、育て上げるために志向した方向性なのです。
「ベッドに横たわるノヴァーリスは、眠りを守っている」[21]ダリヤは日記にそう綴りました。彼女は、ポストモダンに狂い走る西洋によって失われ、無にされた全ての文化―"キャンセルカルチャー"―が、密かにロシアへと移行し、我々がその継承者、後継者、そして復元者になったと信じていました。
ダリヤは、「永遠の政治」を意味する「Politica Aeterna」の概念に基づき、あらゆる現実政治(Realpolitik)、政治行動、政治的発言の根底には、哲学、そして更には文化や宗教があると考えていました。ロシアの政治分析(少なからずアメリカやヨーロッパでも同様ですが)が驚くほど表面的で、自己満足に浸っていることに、彼女は常に衝撃を受けていました。それらは、この国の文化的潜在力やその歴史的瞬間にまったく見合っていませんでした。
まるでロシアの政治学者たちは、ドゥルーズの教えに従い、問題の深淵へと潜ることを止め、陳腐な一般化を越えて考えることなく、事象の表面とその欺瞞的な軌跡だけを観察し続けるかのようでした。それはまるで、文化や文明の深層から見て、息苦しく野蛮な西側のプロパガンダに真剣に反論する勇気がないかのように見えました。
例えば、ロシアとウクライナ、ロシアと西側の対立について、現代の政治アナリスト(ロシアと西側の両方)が提供する浅薄で一面的な分析の次元は、大規模な空間、文明、文化、宗教、世界観、国民性、固定観念の相互作用の根本的な力学を全く反映していないとダリヤは感じていました。あるいは、それらは全く形にならない、実用的で状況的な方法でのみ取り扱われた、というようにです。
彼女にとって、我々の政治科学は、軽率かつ意図的に、地政学、文化学、「文明主義」の天才たち、つまりオズワルド・シュペングラー、アーノルド・トインビー、ピーター・サヴィツキー、ニコライ・ダニレフスキー、コンスタンチン・レオンティエフ、カール・ハウスホーファー、ハルフォード・マッキンダー、カール・シュミット、フェルナン・ブローデル、アントニオ・グラムシらが書いたことの多くを忘れてしまっているかのようでした。これらの偉人たちの仕事は、大規模な地政学的、文化的な衝突、対立、文明の交流の論理に焦点を当てており、今日では極めて重要性を増しています。
ダリヤは常に不思議に思っていました。それは、シュペングラーの考え方がなぜ忘れ去られ、多極世界の構築においての論点として活用されていないのかということです。彼の考え方は、世界文化や「精神の時代」を、誕生、繁栄、そして衰退というサイクルを生きる一連の有機体と捉え、それぞれの文明に特有の魂のタイプ・「アポロン型」「魔術型」「ファウスト型」・によってそれらが生きているという視点を持っていました。このアプローチは非常に有益であると彼女は認識していました。
驚くべきことに、現代のアメリカの政治学者であるS.ハンティントンですら、彼の「文明の衝突」という理論が全体として注目されていない現状に彼女は困惑していました。この理論は、彼の対立者であるF.フクヤマの「歴史の終焉」説が崩壊した後に、その正当性を証明しました。
一方、ダリヤの父親の作品についても、彼女と彼女の家族全員は深い困惑を覚えていました。彼の父親は、「ヌーマキア:精神の戦争」という重要な知的エピックの著者であり、その中で彼は、ロシアの政治学と地政学、世界とロシアの哲学の歴史、さらには文明の基礎について述べ、世界文明のパラダイムとそれらの時系列的かつ同時的な対立の論理を論理的かつ明確に描き出していました。それにもかかわらず、これらの作品はほとんど利用されていないように見えました。
ダリヤは、これらの無尽蔵に貴重な理論、戦略、思考体系を研究し、普及するために、自身の時間とエネルギーのほぼ全てを捧げました。彼女が政治に注目していたのは、カール・グスタフ・ユングの「深層心理学」になぞらえて「深層の政治学」とでも称するべきものでした。それは、日常的でありながらも深遠な次元を内包し、通常の政治ニュースを正確に解釈することが、歴史の大きな意味を理解する上での啓示に繋がると信じていたのです。
「ハイデガーについての余談」
ダリヤは、我々が歴史の重要な節目に立っていると信じていました。過去の偉大な思想家たちが描いた真理の瞬間がすべて具現化されつつあるこの時代こそが、まさにその時であると。彼女はハイデガーの考えを引き継ぎ、"私達がまだ思考する技術を身につけていないことが最大の危険であり、世界の状態が日増しに危険になっているにもかかわらず"[22]我々は意味付けを試みる思考に対して準備ができていないと感じていました。
ハイデガーの信念によれば、「思考する者とは哲学者であり、思考の舞台とは主に哲学の領域である。」[23]
したがって、哲学者の責任は、自身の意志で日常生活の雑事(Alltäglichkeit)から解放され、自らの使命である「思考」に向かうことです。ダリヤは、思考への道は特定の内的変容、つまり自己改革の果てにのみ開かれると主張しました。
ハイデガーは「思考への飛躍」という概念を提案しました。それは我々をただ別の場所に移すだけでなく、全く新たな領域に連れて行く跳躍です。ここでも、緊張感、意志力、集中力が求められます。[24] そしてさらに、漸進的なレベルの進化からの脱却が求められます。[25] レベルの断絶、つまり一つの存在と理解のレベルから次の高いレベルへの移行という問題は、ダリヤが自身の論文や講演で何度も取り上げてきました。
ダリヤは自身の日記で「自己や思考との衝突から逃げることをやめなければならない」[26]と書いています。つまり、我々は自己や思考から離れる行為を止め、自身の思考と向き合うべきだと彼女は語りかけるのです。
ダリヤは、ハイデガーの作品にいつも敏感でした。そして私たち家族との絶え間ない対話の中で、彼は最近の哲学者の王子であり、古代の堂々たるプラトンのようでした。ハイデガーを理解するためには、思慮深い解釈が求められ、それは解構と解釈学を意味しました。また、魂と心の微調整、細心の注意と忍耐力も必要でした。ダリヤはハイデガーへの道のりを始めたばかりでした。しかしながら、彼の思想は彼女の頭の中にある学術図書館のような本の束ではなく、彼女の人生と絡み合っていました。それは彼女の思考と行動の間に、彼女の詩の変わりゆく間隙に滑り込み、彼女の世界観を形成していました。
彼女は感じていました、考えるということは苦痛で、時としてその重荷から逃げたいと思うこと、そして思考が私たちの全存在を支配し、私たちの人生に食い込み、その形を変えることを。彼女は思考が重く、底なしであることを理解していました。ハイデガーは哲学の本来の課題を「物事をより重く、より複雑にすること」[27]と呼び、哲学は狂気に似ていて、常に時期尚早であると示唆していました[28]。しかし、ハイデガーに従って、私たち親と並ぶダリヤもまた、「哲学は独立した創造的な存在の稀な可能性の一つである」と理解していました[29]。
哲学部の初年度から、ダリヤはディオニュシウス・アレオパギテの否定神学のアイデアに引き込まれ、そのテーマについてのレポートを書いていました。しかし、その高度なキリスト教的プラトニズムと並行して、彼女はハイデガーの対立法と弁証法に触発されました。これにより、「隠されていない」真理が、カタファティックとアポファティックの両面で光を放ち、自己満足の個別の存在、新時代によって概念化された自己充足的で自律的な我々自身から、人間を誘き出すと同時に隠れています。そして、ポストモダンでは、それは外部から制御される分割可能な存在となり、分子や粒子に分解され、断崖からどこかへと向かう存在に変貌を遂げました。
ハイデガーは、真理として明らかにされたもの(「アレテイア」、「覆い隠し」)は「証明することはできない(中略)その代わりに、我々はその非隠蔽性において自己を開示するものをただ指し示し、そして同時に、この指し示しの中で自分自身を示すべきだ。」[30]と述べていました。彼にとって、この単純な指し示しこそが思考の主要な特性であるというのです。
「私達の中にある何が思考を生み出すのか」
ハイデガーは、人間にとって最も重要で本質的なものについて考える難しさを次のように説明しています。「理解が求められるものは人間から逃げる。それは人間から遠ざかり、自己を隠す。しかし、その隠されたものはすでに我々の前に絶えず存在している。そうして自己を隠すことにより遠ざかるものは、私たちへの出現を拒むものの、消え去るわけではない。しかし、この遠ざかりは虚無ではない。これは、現れとともに隠蔽し、出来事(Ereignis)である。そして遠ざかることによって、それはより本質的に人間に向き合い、求められることにより、それに触れる、またそれに関連するあらゆる存在よりも深く、人間を要求する[31]。」
また、「しかし、我々が"向かって引き寄せられる”ものに引き込まれると、我々の本質はすでに鋳造されている。つまり、これにより、つまり“向かって引き寄せられる”ことにより、我々は我々自身、つまり我々自身の存在となる。この指示が我々の本質である。我々は、遠ざかることを示す者である。指示者として、人間は指示者である(中略)人間は記号である[32]」と述べています。
これら全てをどのように理解すればよいのでしょうか?人間の「遠ざかり」は何を意味し、その遠ざかりはどこへ向かうのでしょうか?なぜ「人間は記号」なのでしょうか?そして「何の記号」なのでしょうか?これら全てを他の言葉で表現することは可能でしょうか?おそらくそれは無理でしょう。しかし、ハイデガー自身を少しばかり脱構築してみましょう。脱構築は私たち家族の楽しむ趣味であり、ダリヤはその深過ぎる言語的・精神的作業にいくつかのスキルを身につけています。
ハイデガーにおける「思考」について解説します。ハイデガーは西洋の長い現象学の伝統が収束した哲学の流派を代表しています。この伝統では、意識は現象学者が存在する唯一の場所であり、意識の領域は全てを包含します。外部の世界は、意識の中で表象され、それがまさしく彼の作業の成果となるものです。
ただし、これは攻撃的で、侵略的な、または個々の「我」の意志が強すぎる仕事ではなく、一方で、感知のコンテクストや背景、そして「間」の世界の微細な振動を捉える、繊細な作業です。現象学者は「現象」を研究します。それは私たちの意識の全体的な閃光、生活(認知)行為の要素が結合し、一つに融合し、互いに溶け込む現象を意味します。
これに対して、現象学者以前の哲学者たちは、主に合理主義者のデカルトのスタンダード、つまり、互いに外部で独立した、現代の能動的な主体と受動的なオブジェクトの外部に基づいて考える傾向がありました。
現象学的に理解される「思考」は、人間の存在を思考すること、それは一つのプロセス、一つの流れ、感覚やそれに伴う経験、知覚、想像力の川のようなものと言えます。現象学者は常に意識の内部にいます。彼にとっての外部世界は意識の境界上にあるのです。
意識の構造において、現象学者は「ノエシス」(νόησις)、つまり「ホロス」(ὅλος)、生命的で認識的な行為そのものの完全性、そしてその意識の指向性(in-tentio)、つまりその向かい合う方向性を含んでいます。それは世界への意識的な関与の過程で生じる表象(Vorstellung)であり、そしてそれはそのままオブジェクト(Inhalt des intentionalen Akten)、認識的視点の焦点となる現象学で「ノエマ」(νόημα)と呼ばれるものとなります。これはダリヤからの説明です。
現象学的な行為において視線の源、つまり意識と意識に近い領域を照らし出すスポットライトの光が発せられる地点が存在するのかどうか。それとも、見て理解するものや者が存在するのかどうか、という問いについてダリヤは常に興味を持っていました。彼女はこの問題を、ハイデガーが追求した現象学的な主題としてとても重要で、洗練されていると見ていました。我々一家で、この問題を様々な視点から、さまざまな文脈で何度も議論したことを思い出します。
ダリヤが提示した答えは、ダーザインの「誰」または「何」について、知恵に満ち、不思議なものでした。「この誰か」や「何か」について何かを理解しようとすると、それは人間のダーザインの深淵をのぞき込み、そこに飛び込み、隠れ、自己を示すこの名前のない「主体」についてのみ可能となります。ただし、これが可能になるのは、ダーザインが拒否するときだけです。ここで、彼女の音楽プロジェクトの謎めかした名前「Dasein may refuse」が再び浮かび上がります。
近代では「主体」と「客体」として知られていたものは、現象学においてはより複雑で柔軟、そして奇妙なものになります。相互作用の衝動を最初に発するのは誰なのでしょうか。それは人間なのでしょうか。そしてその能力は何なのでしょうか。自己自足で自律的なものなのでしょうか。周辺視野の断片を注意の中心に移すのは何なのでしょうか。私たちはそれをどのように行い、どのような「助力者」を利用するのでしょうか。ただし、対象を注意の中心に持ってきてその表象を固定することは、本質的に考えることではなく、その構造的な成分に過ぎないということを理解しなければなりません。では、我々が思考するとは、具体的に何を意味するのでしょうか。
ハイデガーは、人間を惹きつけながら同時に人間から遠ざかり、自分自身を隠しつつ、どんな存在よりも深く人間に触れ、人間に本質的に対峙し、人間を求めて要求する、神秘的な何かについて語ります。この神秘的な起源は、人間に「触れ」、「到着」し(増大し)、その「到着を達成」し、私たちの本質(unser Wesen ... geprägt)を「形成」することによって、私たちを人間にするのです。私たちの存在、私たちの生存、私たちの本質の源とは何なのでしょうか?
この問いに対しては、ダリヤと一緒に、我々は間接的な回答しか提供できません。
私たちは正教の文化に生きており、キリスト教を正式に捨て去ったドイツの哲学者に魅了されているという事実は、問題があるように見えるかもしれません。しかし、注意深く見れば、ハイデガーの思考の多くの動きが、我々の正教の伝統(特に修道士の禁欲主義)に直接対応していることがわかります。具体的な感知・体験の行為を超えて、つかみどころのないものが我々を惹きつけているその何かが、現象の裏側からは、神の呼び掛けであり、我々の内部の神への憧れであると理解できるのです。言い換えれば、ハイデガーの存在論的分析は、正教の伝統における知識の探求の段階、天上の世界を求める魂の神への探求と一致することができるのです。
Jobim may refuse
詩的に言えば、ダゼインとは何でしょうか?それは人間の意識の中に微細に存在し、生命の流れとも言える要素なのです。これはゲームのようでもあり、川の流れのようでもある。それは自分自身の知覚、階層、好みを自由に配置し、それらをリセットし、混ぜ合わせ、新たな構造を築くことです。おそらく、ダゼインとは、アントニオ・カルロス・ジョビンが「3月の水」で歌っていたものでしょう。なお、「3月の水」の3月は、偉大なボサノヴァの作曲家であるジョビンが曲を作った南半球では秋を意味します[33]。
Это дерево, это камень,
Это конец дороги,
Это то, что осталось от пня,
Это чуть-чуть одиночества.
Это осколок стекла,
Это жизнь, это солнце,
Это ночь, это смерть,
Это ловушка, это рыболовный крючок (…)
Это мартовские воды, завершающие лето.
Это обещание того, что я буду жить в твоем сердце.
É pau, é pedra,
é o fim do caminho
É um resto de toco,
é um pouco sozinho
É um caco de vidro,
é a vida, é o sol
É a noite, é a morte,
é o laço, é o anzol
(…)
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração.
棒きれ 小石
この道の終わり
木の切り株 少しの寂しさ
ガラスのかけら 人生 太陽
これは人生 これは太陽
それは夜 それは死
それは罠 それは釣り針(...)
夏を終わらせる三月の水たち
それは 私があなたの心の中で生きるという約束
ダリヤは、幼少の頃から父が愛した音楽であるボサノヴァの古典を聴き続けてきました。その後、彼女はハイデガーの著作を読むようになり、彼のテキストの解釈や翻訳、それらを中心とした家族の会話や、アレクサンドル・ドゥーギンのセミナーや講義を耐えることとなりました。それはジョビンの瞑想的な印象派音楽とその洗練された落ち着いた音楽的言葉が、彼の言葉の爆発的で心を打つ意味と対照をなし、どういうわけか、ハイデガーの人間の世界への「棄てられた」存在のテーマに重なりました。
そしてそれは、ドイツの哲学者が人間と世界の物事との詩的な関係についての洞察や、人間だけが自己の有限性や死を理解し、それを世界で唯一の、例外的な生命として理解するという彼の考えとも一致しました。ハイデガーの実存主義的な「死への存在」の概念と、ジョビンがポルトガルの詩から引用した「saudade」のアイデアは驚くほど互いに共鳴しています。
「saudade」の神秘的な悲しみは、過去の人々や出来事への郷愁、失われた親しい人への執着、失われた愛、人々、機会への渇望、現在の喪失を経験すること、優しさと悲しみ("tristeza")、無欣喜の気分、憂鬱、そして哀悼といった多層的な意味を持つ、翻訳不能な単語(「欠席の存在」)です。
ジョビンの音楽の中のこれらの感情は、印象派のアカデミックスクール(ショパン、ドビュッシー、ブラームス)に触発された軽やかで、表面上はケアフリーな無調の短調・長調のメロディと対照をなしています。それはクール・ジャズとサンバのリズムによって補強されています。つまり、私たちは人生のある瞬間で、ハイデガーの哲学的なエスキュリアルとブラジルのボサノヴァのメランコリックな宮殿に同時に足を踏み入れました。そして、ダリヤはその時、私たちと共にそこにいました。
「魂の理想郷(「魂の城」、「火花」、「心の深層」…とその他の素晴らしいテーマ)」
マルティン・ハイデガーの中心的概念である「Dasein(ダーザイン、『ここに存在する』)」は、人間の自由と世界への完全な関与の領域と見ることができます。これは、意識と対立する外部の対象としてではなく、意識が世界に存在する、あるいは世界が意識に存在するという内的な存在として理解されるものです。この概念は、「ここと今」の瞬間の体験を通じて明らかになり、言語、感情、精神の動きに表現され、行動を照らし出し、哲学的・政治的実践の中で生き続けます。
Daseinは、「ここに存在する」瞬間を全体として体験する人間の状態であり、同時にハイデガーが具体的に名前を挙げていない特別な存在、鋭い観察者との出会いを予感させるものです。その存在は、私たちの内側から、私たちの意識の限界で、私たちの視線のすぐ裏から、静かに現れ、私たちの視線を導きます。
ハイデガー自身はカトリックの家庭で生まれ、1909年にはイエズス会の修道院で修道誓願を立てることを考えていました。その後、2年間神学部で学んだ後、フライブルク大学の哲学部に移りました。もちろん、彼は中世の神学者たちの作品を熱心に読み、ヨハン・タウラー、マイスター・エックハルト、ディートリヒ・フォン・フライブルク、ヤコブ・ベーメといったドイツの神秘主義者に強い関心を持っていました。
それは言うまでもないことですが、これら全ての状況は、私たちがハイデガーを、中世ドイツの神学者や哲学者により描かれた重要な問題の観点から観察するのに適した環境を提供してくれました。そして、これらの問題について知ることは、私たちの知的な洗練度を証明するだけでなく、現象学そのものへの鍵、特にハイデガーの現象学を理解する鍵を握る証となりました。そして何より、それは人類の歴史と現代世界における主体性、特に「急進的主体」[34]という問題への理解を深める手がかりとなりました。
これらのテーマ、特にアレクサンドル・ドゥーギンが青年時代に知識人の友人たち(ヘイダル・ジェマルとエフゲニイ・ゴロヴィン)との会話を通じて育てた「急進的主体」についてのテーマは、彼自身が認めるように、彼の思考を一種の壮大な哲学的啓示で照らし出しました。このテーマは私たち家族の仕事、私生活、そして活動の中で度々話し合われました。宗教的な神秘主義者たちの主要なテーゼは、その大半が、アリストテレス的なテーマである能動的と受動的な理性、そして神と人間の間のそれらの関係についてのドイツの神秘主義者たちによる解釈の性格に集約されていました。これは、「急進的主体」というテーマを理解するために重要でした。
ドイツの神秘主義者たちはそれぞれが、この視点から哲学的に美しく、鮮やかで価値ある何かを創り出しました。M.エックハルトは、人間と神との間の結びつきを表す魂の火花(vunkeln)や、人間の心深くに降り注ぐ神の光について書きました。それはまるで人間の心が城であり、神の光がその城(Seelenburg)の内部の壁に反射するかのようです。その反射により、人間はキリスト教的視点から神と直接接触し、神の子として生まれ、その子の現実化を経験する魂の理想的な町が創造されるのです。
ヤコブ・ベーメは、豪雨のように人間の魂を打ちのめし、稲妻のように鮮烈な印象を与え、神聖な感触をもつ黄金の糸のような啓示について語りました。その瞬間に敏感である人、それを心待ちにしている人、その呼びかけを聞く人、そしてそのようなつながりを求める人だけが、自分の内なる宮殿の扉の前で永遠に俗物とされることなく、自身の魂の秘宝へと進むことができます。
ディートリッヒ・フォン・フライベルク(テュートニクス)は、「私たちの中で考えているのは誰なのか?」という問いを再び提起しました。アリストテレスやヘーゲルに続いて、哲学者は結局のところ神自身が哲学していると考えていたフライベルクは、人間には2種類の知性が働いていると指摘しました。それは、「νοῦς ποιητικός」、つまり「創造的な心」である能動的な知性と、「νοῦς παθητικός」、つまり「受け身の心」である受動的な知性です。人間における能動的な知性は、不動の原動力である神が私たちを通じて考えると考えられてきました。この知性は人間において創造されたものであり、一方で神自身の知性は創造されていないとされています。したがって、人間において神は仲介者である天使の階層を通じて考えています。したがって、能動的な知性は、人間における被造的な神、すなわち恵みによる神のような存在と言えます。神の心と人間の心の一体化の神秘は、人間の内なる秘密の部屋、心の最奥部、アブディトゥス・メンティスで起こるのです。
「日々の重荷:耐えがたき日常」
ハイデガーは、現代人が日常生活(doxa、Alltäglichkeit)の安定した構造に安住する傾向があることを認識し、それを人間の第一の、凡庸な面とみなしました。そして彼はもう一つの側面を挙げました。それは、自身の中における自己の存在、すなわち能動的な知性へと向かう人間の覚醒の可能性です。ダリヤとともに、私たちは全員でハイデガーがアリストテレスとドイツの神秘主義者に触発されて能動的知性というテーマを発見したことを喜びました。
彼によれば、「日常生活」の構造は自己完結しているわけではなく、内部から見つめる鋭い視線によって貫かれています。人間の中には、あまり認識されていない、名前のないアポファティック(否定的な)な側面が存在し、その存在は見かけ上の幸福を破壊し、その源泉と目的が不明な深いノスタルジーを人生に注ぎ込むことが明らかになりました。
さらに、私たちの家族における哲学的な立ち位置から見ても、ハイデガーの現象学的なプロセス(ノエシス)を通じて、人間の「内部の祭壇」、「秘密の部屋」の門前に立つ、その存在を見守り、指導する、名前のない神秘的な保護者の姿が見えてきます。そして、この同じ明るい影は、人間の「放棄」の環境における特定の「ここ」、そのDaseinの中に広がっていることがわかります。
この明るい影は、アントニオ・カルロス・ジョビンの瞑想、彼のサウダージュ(ノスタルジー)とトリステーザ(悲しみ)にも映し出されています。それらを通じて、Dasein自体が、昼と夜、水と道、ガラスと太陽、生と愛、死とさえも、そして私たちのノエティックな視点を保護し、導く存在、つまり、目には見えない指揮者のジェスチャーを用いて私たちに語りかけているのです。
「ダーゼインの救済」
ダリヤが「Dasein(ダーゼイン)は拒否することができる」という表現を用いた意味について、異なる解釈を選ぶこともできます。
私たちがかつて彼女と話し合ったことによれば、ダーゼインは絶対的に保証されるものではなく、私たちに心を開くか、あるいは新郎が花嫁に拒否されるように私たちを拒む可能性があります。ダーゼインは私たちから離れることができます。それにより人は不真実性、突破できない「日常性」、そして平凡性に留まり、ハイデガーが「Gerede(ゲレデ)」、すなわち無意味な会話と称した日常の意識の型に囚われます。そのとき、ダーゼインは「Das Man(ダス・マン)」へと変わるでしょう。これは、自己が鮮烈に生きるのではなく、何となく自らを生きる状態を指します。また、自分が話すわけでも考えるわけでもなく、むしろ一見普遍的ながら実際にはつかみどころがなく、恐らく存在しない不特定多数の誰かが言葉を発し、思考する状況を指します。
ダーゼインの代替とは、死ではなく、現代世界の強制収容所である存在、つまり、真正性、真理、思考を超越した存在の動物園、あるいは無限に繰り返されるレコード「Das Man(ダス・マン)」の迷宮に存在するという呪いです。
考えるために必要なのは存在そのものではなく、存在の存在です。ハイデガーは「存在の存在は、存在するものの存在、存在するものの存在を意味する[35]」と述べています。そして、我々はこの意味を既に理解しているかもしれません。ハイデガーに影響を与えたドイツの神秘主義者たちを考慮に入れると、彼らの言葉を用いて、人間の内部に存在する神の息吹、或いは神々の息吹の考えについて話すことができます。これらは古代ギリシャの英雄に未来の洞察力や戦闘での確かな技術を与え、英雄を守り、指導しました。これらは日常を超越し、異なる世界を視覚化し、異なる天空、異なる次元と力を見つめる人々だけです。そして、これこそが英雄であるということです。ダリヤは、まさにこの意味での英雄になることを夢見ていました。彼女は、存在の輝きを受け、完全性への道を追求する名目で人間の限界を超え、終わりまで、そして全てに反して、祖国と精神とともにいることを望んでいたのです。
「我々は本当に意味のない符号にすぎないのだろうか。」
ハイデガーが引用したヘルダーリンは、「私たちは意味を成さない印であり、痛みを感じない」[36]と言っていた。これは、私たち人間が日常的な凡庸さ、覚醒していない状態、人類の降下をめぐる歪んだ転換に無感覚でいる痛ましい状態を指している。
私たちは、何を示す印となっているのでしょうか?そして、私たちが痛みを感じない理由は、本当の思考や理解の源泉となる場所、正しい岸辺や地域にいないからなのでしょうか?なぜ私たちは、何か偶然で重要でない、無意味なものの無益な記号になるのでしょうか?ハイデガーはこの問いに対して、深く、心を動かす回答を与えています。しかし今日、私たちはどのような答えを出すのでしょうか?
「もしも今日、この戦争の状況により、我々は何かを感じ、理解するようになるのかもしれません。人間として、我々が静かに容認してきた世界の苦痛、その状況に自身が傷つくことについてです。」と、ダリヤは日記で深遠な問いを投げかけています。「我々が本物を選び出す、そんな希望が存在するのかもしれません。なぜなら、我々はすでに新たな領域に足を踏み入れています。そこは、まさに思考の原風景が開かれる場所であり、歴史的な出来事が既に動き出しています。神話が暴かれ、理論、概念、原理、パラダイム、軍隊といったものが交錯し、対立する場所なのです。
今日、我々はアングロサクソン文明のグローバリズムと植民地主義の進行を、鋭く、そして明瞭に目の当たりにしています。そして、新たに現れた多極的な世界観と、多様な文明が開花するという考え方が、命を吸い取られていく世界的な人類という西洋の一元的な観念に反対していることにも立ち会っています。
思想的にも道義的にも疑念を抱かざるを得ないグローバルな寡頭者たち、金融家たち、政治工作家たちが主導する西洋文明の開発計画は、我々人類にとって全くと言っていいほど満足できるものではない、と我々はますます認識しています。リベラルなグローバリストたちは、平面的で明白な反人間主義的な人間観を発展させ、押し付けてきています。彼らは世界の歴史を全ての知的な権力を機械やAIに犯罪的に移譲することで解釈し、管理下に置かれた感染病、性の変更、遺伝子改変、電子的な義肢などを通じて、人類そのものを絶滅させる計画を立てているのです。
彼らは各民族の伝統と宗教を混ぜ合わせ、差別し、一族や部族の概念がない改変可能な人間という狂気じみた基準を押し付けてきています。そして、家族や国家、言語や文化を破壊する戦略を策定しています。これら全ては我々がますます明確に認識している事象です。」
このプログラムには哲学的な表現形式もあります。ポストモダニズムは、何ものであれ、それが人間の解体とそのアイデンティティの消滅を求めているのでしょうか?また、「オブジェクト指向の存在論」(OOO)が無情な機械が君臨するポストヒューマンな世界へ文明を準備しているのではないでしょうか?政治と哲学は密接に結びついています。我々は無意味な記号ではないのです、しかしながら我々は強制的にそのようにされていると言えるのです。
「伝統の秘宝を解き明かす」
ダリヤは、現今、全ての障壁に逆らって、我々が人類の知的達成を保管する秘密の保管庫が奇跡的に開示される瞬間に立ち会えることを切望していました。彼女は、現実的な政治や実践的な問題についての議論の文脈に、高度な哲学、神学、宗教、神秘主義、終末論、そして芸術のテーマを組み入れる学びの時が来たと感じていました。
プラトン主義のテーマが現代世界の理解に重要であると彼女は確信しており、なぜ現代世界がプラトン主義に対して攻撃的であるのかの理由が明らかになるだろうと信じていました。また、キリスト教への弁護が再び関連性を持ち、その激しい攻撃が何によって引き起こされるのかを理解する必要があると提唱していたのです。
彼女は、神秘的なアイデアや流派が現代の至る所に散在していることを目の当たりにしましたが、真の叡智の宝はどこにあり、模倣、風刺、そして歪曲はどこにあるのかと問いかけました。ダリヤは、人類がさまざまな民族の伝統が持つ無尽蔵の知的能力をより深く探求し、利用できることを願っていました。
ダリヤの父は、「ヌーマキア」つまり世界の文化と文明についての壮大な24巻のエポスを書き上げ、人間の構造、精神と心の装置、国家と民族の世界、世界観と世界理解についての多様なロゴスや心理学についての対話を始めることを提案しました。彼の後を追い、ダリヤは多次元的かつ多極的な思考を身につけ、人々に教えることを夢見ていました。彼女は、真正の思想との真実の出会いを願い、彼女の魂に訴える真のアイデアによって求められる存在になりたかったのです。
彼女は、世界のグローバルエリートの下働きで、私たちの議論を引き裂き、混乱に陥れ、偽りの非難、捏造された結論と注釈、直接的な禁止とタブーによって私たちを窮地に追いやる知性の商人たちの操縦を暴こうとしていました。彼らは偽りの解釈とその解釈の買収によって、我々を真理と叡智から遠ざけ、世界を注文制の判断、賄賂による理論、そして「予言」で満たすのです。彼らは思考に対する拒否権を行使し、本の禁止を実施し、真に(そしてリベラルではなく)自由な思考に対する制裁を命じます。
ダリヤはこの状況と戦っていました。彼女はまさしく伝統の小さな戦士であり、最後までその伝統に忠実でした。彼女が「伝統」のフェスティバルから帰る途中で亡くなったという事実さえも、象徴的です。彼女は精神の構造の中で生き、死にたかったのです。美しく輝く彼女の人生が、まさにその飛翔の瞬間に闇の力によって絶たれたとしても、彼女は目指したものを達成しました。
彼女の生涯の最後の日に、彼女は父親にこう言いました。「パパ、私は戦士だと気づいたわ。」彼女はそれを体現していました。まさしく伝統の戦士として。
「天の国を手にするために」
広大な視野と洞察力、世界情勢の賢明な見通しという深みと視点は、現代の分析に過剰に詰め込まれた一般的な意識では捉えられません。現代の政治テクノロジストや専門家の頭はパンク寸前で、起こっている事象の超越的なスケールには収まりきりません。彼らは神話を知らず、理解せず、人々の文化的コードを見過ごし、歴史の隠された論理や哲学、伝統、宗教の深遠さを無視します。彼らはそれらを「非科学的」なものとして排除します。しかし、神話、文化、世界観、宗教、伝統は、どの文明においても、人間の生活の最も主要で本質的な部分です。これは人間の存在の構造、骨組みを形成しています。これらすべてを奪い、排除し、無視することは、人間からポストモダンが「大きな物語」「大きな説明」を呼ぶものを奪うことを意味します。一方、私たち伝統派は、これを人間や人々、文明や文化の「真の生活」「真の存在」と呼んでいます。
私たちは今、長い十年の後に初めて、神話、歴史、哲学、伝統、宗教が逆説的に政治学や国際関係の領域へと侵入してきている現象を目撃しています。この領域は過去50年間、実利主義的で冷淡で計算高い理性によってのみ支配されてきました。それとは反対に、深遠な思考が本来あるべき場所、そして現在でも求められている場所に至らないという現状には我慢ならない思いを抱いています。例えば、哲学研究所という機関がなぜまだポストモダンの敵の手中にあるのか、全く理解できません。この要塞は、「アゾフスタル」とは異なり、まだ攻略されていません。
「まだ希望の鳥は心の中にいる」
ダリヤは、私たちが今こそ行動すべき時が来たと考えていました。私たちとは、思索の限界に立つ者、聖職の奉仕者、そしてキリストの後継者のことです。彼女は、神話、伝統、地政学、哲学、文化、そして思考自体を混乱している人々や私たち自身に取り戻し、新たな天上の秩序を地上に築くためには、例外的な努力が必要だと信じていました。つまり、彼女の目指す人道的課題、彼女の目標とは、乾燥した政治管理の領域に文化や哲学を取り込むことでした。
また彼女は、現代のリベラルな個人主義が人間を本質的に自己から遠ざけることに対する、可能な代替策についても考えていました。これは、神の意図や歴史の中での目的から人間が疎外されてしまう現象への対抗策です。彼女のアルバム「Dasein may refuse」に収録された曲の一部には、ルーマニアの詩人でダダイストのトリスタン・ツァラの言葉、「心の中にはまだ鳥がいる」が含まれています。ダリヤは、自分の心の中の鳥たちを解き放つことを望んでいました。
そのために彼女は命を狙われ、憎悪と薬物によって顔を歪めた卑劣な者たちによって破壊されました。だが、それはすでに彼らだけの問題ではなかったのです。彼らの背後には、西側の全世界規模の情報収集機関や特殊計算センターが存在していました。これらはまさに地獄の肖像画を描いており、その中心には地獄の主、サタンが存在していたのです。
「メリトポリの通り」
ダリヤの悲劇的な最期は、彼女を私たちの社会の真の英雄にに押し上げました。彼女、若き美しいロシアの哲学者が恐ろしい犯罪の犠牲となったことは、ロシア国内外の多くの人々を打ちのめしました。知識人であろうと一般の人々であろうと、彼女の著書、ノート、記事、詩、歌が新たに見つけ出され、その魅力に取り組む人々が増えました。彼女の作品はイタリア語や英語、スペイン語、ポルトガル語、さらには日本語にも翻訳され、広く世界に知られるようになったのです。
彼女の魅力は全ての人々を魅了し、彼女自身が一種の象徴となりました。それは明るく高尚な思想、純粋な意図、そして道徳的真理を伝える象徴として、多くの親が子供たちが目指すべき姿、そして子供たち自身がなりたいと願う理想の姿となりました。
2022年の6月、ダリヤがドンバス訪問中に立ち寄った最後の都市、メリトポリでは、その市民たちの願いと市行政の同意により、彼女の名前を冠した通りが誕生しました。それはかつて「大学通り」と呼ばれていた通りです。そしてその大学の建物には、ダリヤを幼少期から知るロシアの優れた芸術家、アレクセイ・ベリャーエフ=ギントフトによる彼女の大きな肖像画が飾られました。そこには美しくも壊れやすい少女の姿が描かれています。
そして、その肖像画のそばには、「ダリヤは我々の魂」という言葉が刻まれています。これはロシア人全体、特に理想と祖国を守るためにドンバスに向かった人々にとって、現代世界との偉大な戦争における神聖な戦場となりました。
これらの文章を書いているいま、決定的な戦いの結果はまだはっきりしていません。全てがギリギリのところで揺れ動いています。そして、ダリヤ・ドゥギナ通りにあるダリヤ・ドゥギナの肖像は、まさにフロンティア、つまり「分裂と結合」「内部と外部」「我々自身と他者」天と地を分ける哲学的境界線に位置しているのです。
真の英雄であるダリヤ・ドゥギナは、常に最前線に立っている。
そして、彼女の存在はこれからもそうあり続けることだろう。
ーーーーーー
[1] Geworfenheit -- «заброшенность», важнейший экзистенциал М. Хайдеггера.
[2] Дугина Д.А. Топи и выси моего сердца. Дневник Даши Дугиной. М.: АСТ, 2023. С. 175.
[3] Дугина Д.А. Топи и выси моего сердца. Дневник Даши Дугиной. С. 413.
[4] Подробнее об этом в курсе лекций А. Дугина «Феноменология Аристотеля». https://paideuma.tv/course/kurs-aristotel-i-fenomenologiya
[5] Платон в «Государстве» признает, что раздраженным трудной истиной невежам вообще свойственно убивать философов, спустившимся на дно пещеры, чтобы освободить узников от иллюзий.
[6] Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная Революция, 2006.
[7] Генон Р. Царство количества и знаки времени. М.: Беловодье, 1994.
[8] Делез Ж. Логика смысла. М.: Академический Проект, 2011. С. 11-12.
[9] Дугина Д.А. Топи и выси моего сердца. Дневник Даши Дугиной. С. 295.
[10] Ницше Ф. Так говорил Заратустра/Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 40.
[11] Генон Р. Царство количества и знаки времени.
[12] Мейясу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности. — Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016.
[13] Brassier R. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. London: Palgrave Macmillan, 2007.
[14] Ланд Н. Дух и зубы. Пермь: Гиле Пресс, 2020. Целиком Land N. Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007. L.: Urbanomic, 2011.
[15] Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альпина Паблишер, 2018.
[16] Дугина Д. Топи и выси моего сердца. Дневник Дарьи Дугиной. С.175
[17] Дугина Д. Топи и выси моего сердца. Дневник Дарьи Дугиной. С. 241.
[18] Дугина Д. Топи и выси моего сердца. Дневник Дарьи Дугиной. С. 180.
[19] Дугина Д. Топи и выси моего сердца. Дневник Дарьи Дугиной. С. 180.
[20] Дугина Д. Топи и выси моего сердца. Дневник Дарьи Дугиной. С. 387.
[21] Дугина Д. Топи и выси моего сердца. Дневник Дарьи Дугиной. С. 359.
[22] Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 2000. S. 130.
[23] Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. S. 130.
[24] Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. S. 133.
[25] Эвола Ю. Оседлать тигра СПб.: Владимир Даль, 2005.
[26] Дугина Д. Топи и выси моего сердца. Дневник Дарьи Дугиной. С.244.
[27] Интервью М. Хайдеггера в журнале "Экспресс". L'Express. 1969. 20-26 oct. P.79-85.
[28] Интервью М. Хайдеггера в журнале "Экспресс".
[29] Интервью М. Хайдеггера в журнале "Экспресс".
[30] Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. S. 134.
[31] Das zu-Denkende wendet sich vom Menschen ab. Es entzieht sich ihm, indem es sich ihm vorenthält.
Das Vorenthaltene aber ist uns stets schon vorgehalten. Was sich nach der Art des Vorenthaltens entzieht, verschwindet nicht. Doch wie können wir von dem, was sich auf solche Weise entzieht, überhaupt das geringste wissen? Wie kommen wir darauf, es auch nur zu nennen? Was sich entzieht, versagt die Ankunft. Allein - das Sichentziehenf ist nicht nichts. Entzug ist hier Vorenthalt und ist als solcher Ereignis. Was sich entzieht, kann den Menschen wesentlicher angehen und inniger in den Anspruch nehmen als jegliches Anwesende, das ihn trifft und betrifft.Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. S. 134.
[32] Sind wir aber als die so Angezogenen auf dem Zuge zu . . . dem uns Ziehenden, dann ist unser Wesen auch schon geprägt, nämlich durch dieses »auf dem Zuge zu . . . «. Als die so Geprägten weisen wir selber auf das Sichentziehende. Wir sind überhaupt nur wir und sind nur die, die wir sind, indem wir in das Sichentziehende weisen. Dieses Weisen ist unser Wesen. Wir sind, indem wir in das Sichentziehende zeigen. Als der dahin Zeigende ist der Mensch der Zeigende. (…) Ist der Mensch ein Zeichen. Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. S. 135.
[33] Даша слушала классиков «bossa nova” c раннего детства, так как это -- любимое музыкальное направление ее отца.
[34] Дугин А. Г. Радикальный Субъект и его дубль. М.: Евразийское движени, 2009.
[35] «Sein des Seienden heißt: Anwesen des Anwesenden, Präsenz des Präsente». Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. S. 141.
[36] «Ein Zeichen sind wir, deutungslos Schmerzlos sind wir». Heidegger M. Vortäge und Aufsätze. S. 135.
翻訳:林田一博
