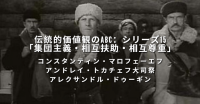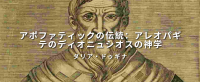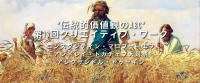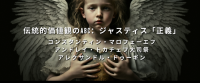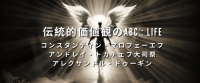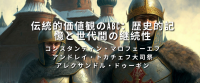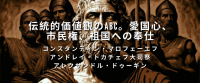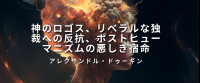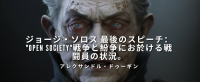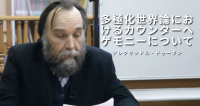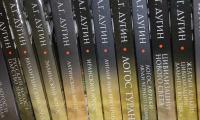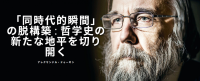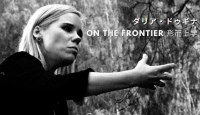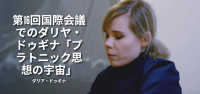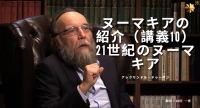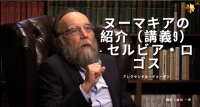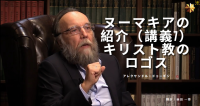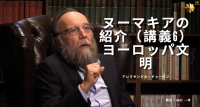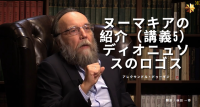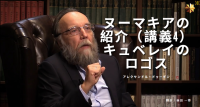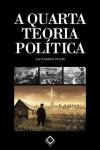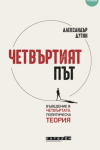伝統的価値観のABC:歴史的記憶と世代間の継続性
ロシアのテレビチャンネル「ツァルグラード」の新企画、3人のロシア人思想家による講演シリーズ「伝統的価値のABC」の第4弾をお届けします。コンスタンティン・マロフェーエフ、アレクサンドル・ドゥーギン、アンドレイ・トカチョフという3人のロシア人思想家によるシリーズです。 私たちは、この国で何十年もの間、相応の注意を払われてこなかったテーマについて議論しています。それは、歴史的な記憶や世代の連続性といった、あらゆる国家の最も重要な価値観の基盤についてである。大統領令第809号で承認された伝統的な精神的・道徳的価値を保存・強化するための国家政策の基本方針では、このような価値観が定式化されているのです。
ジョージ・ソロス 最後のスピーチ:"OPEN SOCIETY"戦争と紛争にお於ける戦闘員の状況。
2023年2月16日、グローバリズム、一極集中、西側覇権の維持の主要な思想家、実践者の一人であるジョージ・ソロスが、ドイツのミュンヘン安全保障会議で画期的ともいえる演説を行った。93歳のソロスは、師であるカール・ポパーの教えに従って、敵である「閉じた社会」に対する「開かれた社会」の闘争に全面的に傾倒し、人生の終盤に自分が置かれた状況を要約しているのである。ハイエクとポパーが自由主義的グローバリズムのマルクスとエンゲルスだとすれば、ポパーはそのレーニンである。ソロスは、時には贅沢なことを言うかもしれないが、全体としては、その時々の世界政治の主要なトレンドとなるものを率直に表現している。彼の意見は、バイデンの無口なおしゃべりやオバマのデマゴギーよりもずっと重要である。リベラル派とグローバリストは皆、ソロスの言うとおりにしてしまう。彼はEU、MI6、CIA、CFR、三極委員会、マクロン、ショルツ、ベルボック、サーカシビリ、ゼレンスキー、サンドゥ、パシニャン、そして西洋、自由主義的価値、ポストモダン、いわゆる「進歩主義」を支持するほぼすべての人々の首謀者である。ソロスは重要だ。そしてこの演説は、世界の「見えない議会」に対する彼のメッセージであり、眠っている者も目覚めている者も含めて、グローバリズムの終わりのないエージェントたちに対する警告である。
「同時代的瞬間」の脱構築 : 哲学史の新たな地平を切り開く
哲学の歴史は、あらかじめ出発点を決めて研究しなければならないことは自明である。それは当然、同時代的な瞬間であると考えるのが自然であろう。同時代的な瞬間とは、「今、ここ」、hic et nunc を意味する。この瞬間が出発点であり、哲学を哲学史として概観するための「観測点」なのです。哲学の歴史は、このように、私たちの方向に向かって展開していきます。これは時間と場所の両方に関わることです。哲学は、その「源流」(例えば、ソクラテス以前の人々)と21世紀の状況(哲学的自省の中で)の間に歴史的に位置づけられるのです。原則として、この時間的ベクトルは多かれ少なかれ反射的であり、それゆえ、哲学のあらゆる分野での主要な(軸となる)学問が哲学史であるのです。この歴史哲学的なベクトルにこだわることで、私たちはこのプロセスに関与する 可能性を獲得し、歴史哲学的な構造における「哲学者」としての自らの立場を確固としたも のとすることができるのです。これは、もし「哲学的」であろうとするならば、私たちの思考が置かれるヌンク、「今」、時間的な部門なのです。
アレクサンドル・ドゥーギンのインタビュー。TBSが撮ってきた。
アレクサンドル・ドゥーギンのインタビュー。TBSが撮ってきた。
ヌーマキアの紹介(講義10) 21世紀のヌーマキア
さて、この講座の最終回、第10回目は、ヌーマキア入門ともいうべき成果物です。第10回目は、21世紀のヌーマキアに捧げます。社会学では、私たちは今、近代からポスト近代への移行、変容の中に生きていると言われています。そこで私たちは、近代をキュベレーのロゴスの帰還、あるいは復讐と位置づけています。では、「ポストモダンのロゴスとは何か」「それはどのようなノロジー構造なのか」と問うことができる。ポストモダンのロゴスとは、ある意味でサイベーレ革命の最終的な完成形です。つまりそれは、それまでのモダニティの論理的な終わり、論理的な帰結をもたらすようなものなのです。だから、ポストモダンの反近代的な言説に惑わされてはいけないのです。ポストモダンは本質的に近代的です。それは近代の本質なのです。それは代替物ではありません。
ヌーマキアの紹介(講義9) - セルビア・ロゴス
セルビア語のロゴスに集中しましょう。まず第一に、セルビア人大罪やセルビア人実存的地平というものが存在することは確実である。それはセルビア人という存在があるからこそ、絶対に確かなのです。そして、セルビア人がいるということは、セルビア的大罪やセルビア的実存的地平というものが存在するということだ。私の知る限り、セルビア人のダーザインをハイデガー的なカテゴリーで完全に記述しようとした人はいませんが、ある程度のレベルまでなら、技術的な課題として残っています。ハイデガーのノーロジー、ダーザイン、実存的地平、存在と時間を知ることについて述べたことを理解すれば、彼のカテゴリー(彼はこれを実存的と呼んだ)をダーザインを記述するための特別なカテゴリーに適用することができるだろう。そして、それをセルビアのダーゼインに適用することが技術的課題である。
ヌーマキアの紹介(講義7) キリスト教のロゴス
第7回目の講義は、キリスト教のロゴスについてです。そこで今度は、キリスト教とキリスト教の伝統について、短いノロジーの分析を行うことにします。これは決して教条的なものではありません。私たちはキリスト教を文化的、社会的、政治的、構造的、哲学的な現象としてとらえています。ですから、キリスト教を擁護したり非難したりすることはありません。私自身、ほとんどが正教徒だと思いますが、キリスト教を正しい方法で扱おうとしています。それは一種のNoologicalな分析です。真理とか異端とか、教義的に正しいとされたもの、異端とされたものを論じることはしないのです。これから話すことはすべてNoologicalな観点、構造的な分析から見ていきます。
ヌーマキアの紹介(講義4)キュベレイのロゴス
インド・ヨーロッパ文化がどのようにして定住段階に至ったのか、そしてこのシフトとヌーマキアの瞬間のこの構造の変化の間に何が起こったのかをよりよく理解するためには、トゥランの周辺にあった存在的な地平が何であったかを考えなければならない。つまり、ツラン族は東ヨーロッパ、アナトリア、バルカン、イラン(ペルシャ)のエラムの領土、そしてインドの空間へとやってきたのである。そして、これらの空間は空っぽでもなんでもなかった。そこには別の文明があり、別の存在地平があり、別の種類の(あるいは同じかもしれないが、これからわかる)ヌーマキアの適切な瞬間があったのである。ヨーロッパ、バルカン、アナトリア、ペルシャ、インドなど、インド・ヨーロッパ以前の文明は何だったのだろうか。私は、第1回や前回の講義と同様、ここでも、インド・ヨーロッパ人が到来する以前のアナトリア、バルカン、ヨーロッパに、非常に古い大女神の文明が存在したとするマリヤ・ギンブタスの概念に従います。
ヌーマキアの紹介(第3講) 印欧語文明のロゴス
意識、人間の心、思考に関する哲学的学問である「ノロジー」に特化した講義を継続して行っています。今日は2つの講義があります。第3回目の講義は、「印欧語文明のロゴス」という名前が付いています。そこで今度は、前の2つの講義で説明した方法論を、具体的な対象、具体的な文明に適用していきます。これまで、3つのロゴス論と実存的な地平と歴史的なものの概念について話してきました。そこで、今度はそれを印欧語文化に適用してみることにします。まず実存的空間についてですが、この概念はさまざまなスケールに適用できます。小さな共同体、中規模の共同体、あるいは大きな共同体、たとえば同じ言語的起源を持つもの同士などです。そして、これから印欧語の実存的空間についてお話しします。印欧語の実存空間とは何でしょうか。それは最も大きな統合の形の一つです。印欧語的実存空間は、印欧語を話す人々が生活する空間と一致します。