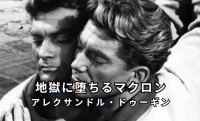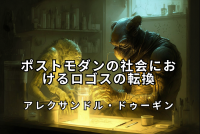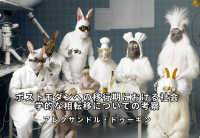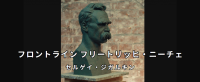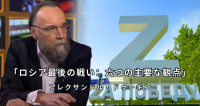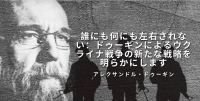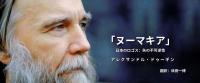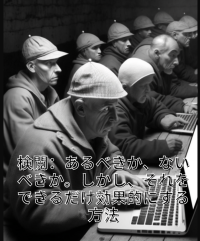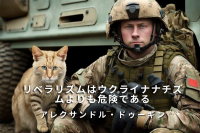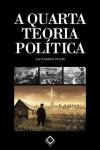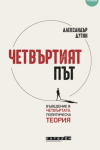地獄に堕ちるマクロン
フランスの街頭で怒りに満ちた人々の暴力的な振る舞いを初めて目の当たりにしたとき、たちまち思うのは「これが革命だ。政府は持ちこたえられない。フランスは終わりだ。政府は倒れるだろう」ということです。抗議するのが、郊外のアラブ系やアフリカ系の若者であったり、ポピュリストの"黄色いジレ"運動の人々であったり、不満を持つ農民であったり、性的マイノリティの支持者や反対者であったり、あるいは家族や伝統的価値観の支持者、ナショナリスト、反ファシスト、アナーキスト、学生、年金受給者、自転車乗り、動物保護活動家、労働組合員(CGT)、環境活動家であったり、彼らの所属や立場は様々です。彼らの群衆は数千人、数万人、数十万人、時には数百万人に膨れ上がります。